numan編集部
声優、アニメ、舞台、ゲームまで!オタク女子のための推し活応援メディア
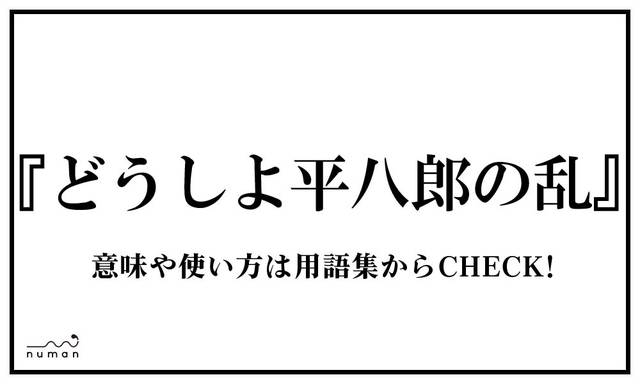
INDEX
一見オヤジギャグにも見えるが、流行させているのは主に中高生。
SNS上などのやりとりで、歴史的人物や事件、有名なフレーズをもじった言葉遊びが流行しており、“どうしよ平八郎の乱”もその流れで誕生した様子。
同様の言葉遊びに、“了解道中膝栗毛”や“尊み秀吉”、”生類わかりみの令”、”春はあげぽよ”などがある。
これらに使われる歴史用語は中高生にとって日本史の授業で学んでいる事柄であり、仲間と共有しやすいのである。
また、Twitterでは、「どうしよ大塩平八郎の乱」と言っている人もたまに見かける。正しくはないが韻を踏んでいるようでテンポよく聞こえるため、意外と違和感はない。
numan編集部
声優、アニメ、舞台、ゲームまで!オタク女子のための推し活応援メディア
本ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合がございます
特集記事
ランキング
電ファミ新着記事